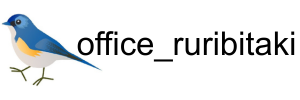日本の公的年金は、原則65歳受給を基準として、「繰上げ」「繰下げ」制度により60歳から75歳の間で受給開始年齢を1か月単位で選ぶことができます。
繰上げ(早く受け取る)・繰下げ(遅く受け取る)によって受取額が次のように変わるため、その選択方法はしばしば話題にのぼります。
・繰上げ制度:1か月繰上げるごとに0.4%減額(最大24%減)されます。
・繰下げ制度:1か月繰下げるごとに0.7%増額(最大84%増)されます。
もし、私がこの話題についてコメントを求められたら、多くのFP同様、「正解はなく、その人それぞれの事情に合わせて受け取り方を選択する」という回答になります。
ただし、その選択において、ベースとなる考え方が2つあることを知っておいてほしいのです。
その2つの考え方とは、年金を「回収すべきもの」とするのか、「セーフティネット」とするのかというものです。
① 年金は「回収すべきもの」であるという考え方
これは、損益分岐点を意識して、どの受給開始時期が有利かを判断する考え方です。65歳受給を基準に考えた場合、答えを導き出すヒントは次のとおりです。
- 繰上げ受給をすれば、支払った保険料の総額を、受け取った年金総額が上回る時期は早く訪れるが、長生きすれば損になる。
- 繰下げ受給をすれば、支払った保険料の総額を、受け取った年金総額が上回る時期は遅く訪れるが、長生きすれば得になる。
このような仕組みを踏まえて、各自がシミュレーションを行い、平均寿命(または平均余命)と照らし合わせながら、自分にとっての着地点を探ることになります。
ちなみに、日本の年金制度は賦課方式(現役世代の保険料を年金支給のための財源とする仕組み)なので、自分が納めた保険料総額と年金受給総額は直接対応しません。
② 年金は“セーフティネット”であるという考え方
この考え方は、金額の損得ではなく、長生きリスクに備えるという保険であるという意味も含まれます。
もし、元気な方であれば、老後の生活費について60代など元気なうちは仕事や投資などでできるだけ賄う。そして、長生きして心身衰えた頃に安定した収入源を確保するという考え方のもと、年金なしで生活できるうちは繰下げを選択するということが考えられます。
このように、“年金をどう受け取るか”は、損得だけでなく、人生設計やその人の価値観によっても大きく異なります。
いずれにしろ、年金額は加入期間や収入で決まるため、1人1人シミュレーションして検討する必要があります。
また、「繰上げ」は老齢基礎年金・老齢厚生年金とも同時に受給が始まることや、「繰下げ」は繰下げ期間中は加給年金が受けられなくなることや、在職老齢年金の影響など、様々に検討すべき事項があります。
受給開始年齢を選べるという制度は、それぞれの人生設計に柔軟に合わせることができますし、受給を開始すれば、その金額は生涯にわたって支給されますので、受け取り方の選択については慎重に検討していただきたいと思います。
ただし、健康状態や生活状況によっては、選択の余地が限られる方もいらっしゃいます。その場合でも、年金が確実に終身で支えとなること自体が安心につながります。よって、この年金制度そのものの継続性がとても重要だと考えています。今後も年金制度については、深掘りしていきたいと思うテーマです。
《補足》
加給年金…
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される制度です。
在職老齢年金…
働きながら年金を受け取る場合に一部支給が調整される制度。この調整については、緩和の方向で改正が予定されており、現役就労を続けながらの年金受給も選択肢の一つとなっています。
2025.11.19